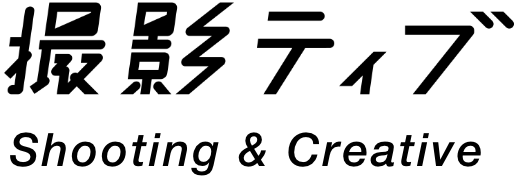SEOライターとは?Webライターとの違い・費用・外注判断を解説

企業のWeb集客やオウンドメディア運用で欠かせない存在となっているのが、「SEOライター」です。しかし実際には、「Webライターとの違いがわからない」「SEOライターに頼むべき案件が見極められない」と感じている担当者も多いのではないでしょうか。
SEOライターとは、単に“検索キーワードを入れて記事を書く人”ではありません。
ユーザーの検索意図を読み解き、記事構成から成果設計までを担う――いわば“戦略的な編集者”です。
本記事では、SEOライターとWebライターの違いを明確にしながら、
・どんなときにSEOライターへ外注すべきか
・内製で進める場合のポイント
・失敗しない依頼の手順と要件定義
を実務者目線で解説します。「これからSEO記事を始めたい」「外注か内製かを検討したい」という広報・マーケティング担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
SEOライターとは?Webライターとの違い

企業のオウンドメディア運用やSEO施策を考えるとき、まず整理しておきたいのが「SEOライター」と「Webライター」の違いです。どちらも“文章を書く仕事”には変わりませんが、目的・関わる工程・評価のされ方が大きく異なります。
この章では、SEOライターの役割や業務内容を整理しながら、Webライターとの具体的な違いを掘り下げます。「自社の記事はどちらのタイプに依頼すべきか」を判断できるよう、成果の出る記事づくりの視点から解説していきます。
SEOライターの役割とは?
SEOライターとは、単に「キーワードを入れて文章を書く人」ではありません。
ユーザーがどんな疑問や課題を持って検索しているのか=検索意図を分析し、記事で解決へ導く設計をするのがSEOライターの役割です。
その目的は「記事を上位表示させること」ではなく、検索結果を通じて事業成果につなげること。
集客・リード獲得・ブランド認知など、企業のゴールから逆算して情報を整理する「戦略型のライター」と言えます。
SEOライターの主な業務内容と関わるフェーズ(構成設計~検証まで)
SEOライターの仕事は、執筆だけにとどまりません。
実際の業務は次のように、記事制作の最初から最後まで関わることが多いです。
1.キーワード選定と検索意図の分析
2.構成案の作成(見出し・導入・全体設計)
3.本文執筆・校正
4.公開後の計測・改善提案
つまり、SEOライターは「書く人」というより、成果を出すための記事構成をデザインする人。記事公開後にSearch Consoleなどで順位やCTRを確認し、改善提案を出すケースも多く見られます。
目的の違い ─ SEOライターは“成果”、Webライターは“読まれる文章”
Webライターの多くは、クライアントから与えられたテーマや構成をもとに文章を書くことが中心です。一方でSEOライターは、「誰の、どんな行動を促すか」まで設計して記事を作る点が大きく異なります。
- Webライター:読まれやすく、読みやすい文章を目指す
- SEOライター:検索上位に入り、成果(CV)につなげる
目的が違えば、記事の設計思想も変わります。SEOライターは文章表現よりも、検索意図と情報設計の整合性を最優先に考えます。
仕事の進め方の違い ─ 構成を設計するか、指示を受けて書くか
Webライターの多くは「構成案をもらって書く」スタイルです。SEOライターは「構成案を自ら作る」ところからスタートします。構成設計では、検索意図をもとに「どんな見出しを立てるか」「どの順番で読者の疑問を解消するか」を設計します。
これは単なる文章力ではなく、論理設計と情報整理のスキルが問われる工程です。この違いが、記事の完成度と成果の差を生む最大の要因になります。
必要スキルの違い ─ 検索意図・情報設計・リサーチ力の3軸
SEOライターに求められるスキルは、文章力だけではありません。代表的な3つのスキルは以下の通りです。
| スキル | 内容 | 重要度 |
| 検索意図分析力 | ユーザーが知りたい“本質的なニーズ”を読み取る | ★★★ |
| 情報設計力 | 構成・見出しで論理的にストーリーを組み立てる | ★★★ |
| リサーチ力 | 競合記事・公的データ・一次情報を調べ、信頼性を高める | ★★☆ |
文章を美しく整えるだけでは、成果は出ません。検索意図を理解し、ユーザーと企業の目的をつなぐ設計力こそが、SEOライターの真価です。
成果の測り方の違い ─ 「納品」で終わるか、「結果」で終わるか
Webライターの仕事は、納品した時点で完結することがほとんどです。一方でSEOライターは、記事公開後の結果まで追います。たとえば「検索順位」「クリック率(CTR)」「流入数」「CVR(成果率)」などの指標をもとに、記事の改善を提案します。つまりSEOライターは、“成果責任を持つ書き手”。
クライアントや企業にとっては「継続的に相談できるパートナー」としての存在価値が高まります。
依頼時の注意点 ─ “SEOに強い”の言葉を見極めるチェックポイント
最近では「SEOに強いライター」を名乗る人も増えています。しかし、すべてのライターが検索意図分析や構成設計を実務レベルで行えるわけではありません。依頼時には、以下のポイントを確認するのがおすすめです。
- 過去に担当した記事の検索順位・流入実績を提示できるか
- 構成案や見出し設計を自ら作成しているか
- 競合分析・リライト提案まで行った経験があるか
“SEOライター”の肩書きよりも、実際の思考プロセスと成果事例を見極めることが重要です。
ここを見誤ると、「SEOを意識したつもりの記事」になってしまうので注意しましょう。
✅ まとめ
・SEOライターは“検索意図から成果まで設計するライター”
・Webライターは“与えられたテーマを読みやすく書くライター”
・違いは、目的・工程・評価軸・関わる範囲にある
この違いを理解しておくことで、依頼先の選定や体制づくりがより明確になります。
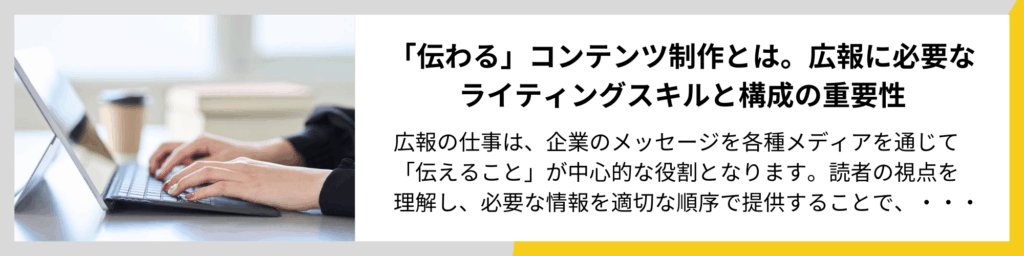
外注か内製か?成果につながる判断のフレーム

SEOライターの役割を理解したところで、次に考えたいのが「自社ではどこまで対応できるのか」という点です。記事制作をすべて外注するべきか、それとも社内で書ける部分を残すべきか。この判断を誤ると、コストばかりかかって成果が出ないという結果になりかねません。
SEO記事制作には、「構成を作る」「書く」「検証する」といった複数の工程があり、求められるスキルも異なります。自社のリソースや担当者のスキル、運用スピードに合わせて、外注と内製のバランスを設計することが重要です。
この章では、
- 外注と内製を分ける判断基準
- 費用と工数の目安
- 成果を最大化するハイブリッド運用の考え方
を整理し、企業が「自社にとって最も合理的な制作体制」を見つけられるように解説していきます。
外注と内製を分ける3つの基準(スキル・スピード・レビュー体制)
SEO記事制作を自社で行うか、外部のSEOライターに依頼するかを判断する際には、感覚ではなく客観的な基準を持つことが大切です。撮影ティブでは、次の3つの観点で整理することを推奨しています。
1. スキル
SEOライティングには、「検索意図の理解」「構成設計」「分析」の3スキルが不可欠です。
社内にこれらをカバーできるメンバーがいる場合は内製化が可能ですが、
経験が浅い場合やリソースが限られている場合は、専門ライターに外注する方が早く成果を出せます。
2. スピード
SEO記事は“出して終わり”ではなく、定期的な更新と改善が欠かせません。
もし制作が社内のスケジュールに埋もれてしまうようなら、外注でスピードを担保するのが現実的です。
特にキャンペーンや季節特集などタイムリーな記事発信が必要な場合は、外部リソースを活用することで機会損失を防げます。
3. レビュー体制
SEO記事は、ライターの執筆だけでなくチェック体制の質によっても成果が左右されます。
構成・内容・表現・SEO要素をレビューできる人が社内にいるかどうか。
ここが欠ける場合は、編集者やSEOディレクターを含む外部チームに任せる方が安定した品質を保てます。
この3つの視点で社内体制を見直すと、「どの工程を外注すべきか」「どこを内製で持つべきか」が明確になります。次の章では、実際の費用相場と内訳をもとに、外注時にかかるコストと注意点を整理します。
SEOライターの費用相場と費用構成
SEOライターへの外注費用は、「どこまでの工程を依頼するか」で大きく変わります。
単なる執筆だけでなく、構成設計やキーワード分析、公開後の改善提案までを含むかどうかが、コストの分かれ目になります。
| 依頼範囲 | 料金相場(1記事あたり) | 内容の例 |
| 執筆のみ | 1〜3万円前後 | 構成案支給・本文執筆中心 |
| 構成+執筆 | 3〜6万円前後 | キーワード設計・構成提案・本文執筆 |
| 構成+執筆+分析 | 6〜10万円以上 | 成果計測・改善提案まで対応 |
上記はあくまで目安ですが、記事単価=作業時間ではなく「成果を出すまでの設計力」への対価と考えると分かりやすいです。経験豊富なSEOライターほど、分析や改善までを含めた“編集的支援”を提供する傾向があります。
【コストを構成する主な要素】
SEO記事制作の費用は、以下のような工程ごとに分解できます。
①キーワード・競合分析費 … 市場調査・意図分類・構成方針の策定
②構成設計費 … 見出し設計、記事全体のストーリー構築
③執筆費 … 本文執筆・リサーチ・引用整備
④校正・編集費 … 表現・事実確認・SEOチェック
⑤分析・改善費 … 公開後の順位・流入データ分析、リライト提案
たとえば、構成と執筆を分けて発注すればコストを抑えつつ、社内編集で最終調整するなどのハイブリッド運用も可能です。
【費用を検討する際のポイント】
・安さだけで判断しない:記事単価よりも「成果までの伴走範囲」を確認
・記事本数ではなく目的から設計:月○本よりも「どのテーマで何を狙うか」
・継続依頼を前提にした相談:単発よりも、長期的改善を見据えた契約で品質を安定化
SEOライティングは「買い切りの文章」ではなく、“資産になる記事”を設計する投資。自社の目的に合わせて、最適な依頼範囲を選ぶことが成果への第一歩です。
内製で成功する会社・外注が向いている会社
SEO記事制作を成功させるためには、単に「ライターの腕」だけでなく、体制と目的の整合性が重要です。自社の状況やリソースによって、内製化が向くケースと外注したほうが効率的なケースは明確に分かれます。
【内製で成功する会社の特徴】
内製化に向いているのは、次のような条件を満たす企業です。
- 自社の商品・サービスに深い理解を持つメンバーがいる
- 検索意図を踏まえた構成やリライトができる人材がいる
- 記事の品質をレビュー・改善できる体制がある
- 中長期で記事を積み上げていく時間とリソースを確保できる
こうした企業は、“ブランドの語り口や価値観”を統一した発信ができるため、SEO記事にも独自性が生まれやすい。また、社内でPDCAを回せるため、長期的にはコストパフォーマンスが高くなります。一方で、初期段階では記事品質が安定しにくく、成果が出るまでに時間がかかる点には注意が必要です。
【外注が向いている会社の特徴】
外注に向くのは、以下のようなケースです。
- SEOの知見が社内に少なく、構成設計のノウハウがない
- 広報・マーケ担当が他業務と兼任で、執筆リソースが足りない
- スピードを重視したコンテンツ量産が必要
- 客観的な第三者の視点で記事品質を高めたい
特に、新規メディアの立ち上げ期やSEO改善の初期フェーズでは、外部の専門ライターや編集者を活用することで、効率よく“成果が出る型”を作ることができます。
・判断のポイント
どちらか一方に決める必要はありません。最も効果的なのは、内製と外注を組み合わせた“ハイブリッド運用”です。記事の方向性や構成を専門家に任せ、執筆や最終レビューを社内で行うなど、段階的にノウハウを蓄積していく方法が現実的です。次の章では、この“ハイブリッド運用”をどのように設計すれば成果につながるかを解説します。
ハイブリッド運用のすすめ ─ 構成外注+本文内製でコストを最適化
「外注か内製か」で悩む企業におすすめなのが、構成を外注し、本文執筆を内製で行うハイブリッド運用です。この方法は、コストを抑えつつ品質とスピードの両立を図れる現実的な選択肢です。
【構成外注のメリット】
SEO記事の“設計図”である構成は、成果を左右する最も重要なパートです。経験豊富なSEOライターや編集者に構成を依頼することで、検索意図を正しく読み取った戦略的な土台が作れます。
特に次のような工程を外注するのが効果的です。
- キーワード選定と検索意図の整理
- 記事構成案の作成(見出し・順序・情報の深さ)
- 競合記事の分析と差別化ポイントの設計
構成をプロに任せることで、社内メンバーは「正しい設計図」に沿ってスムーズに執筆でき、方向性のズレや修正コストを大幅に減らせます。
【本文内製のメリット】
一方、本文執筆を社内で行うことで、自社ならではの一次情報やブランドトーンを反映しやすくなります。社員インタビューや社内ノウハウ、顧客事例など、社外のライターには書けないリアルな情報を記事に盛り込めるのが強みです。また、記事を社内で書くことで、チーム内にSEOの考え方が徐々に浸透し、将来的に「構成から執筆まで」を内製化できる基盤が整っていきます。
・成果を最大化する運用のポイント
ハイブリッド運用を成功させるためには、次の3点を意識すると効果的です。
- 構成納品時に意図を共有する
外注ライターが作成した構成書には、検索意図や狙いが記載されています。執筆者がそれを正しく理解してから書くことが重要です。 - 社内レビューでブランドトーンを整える
執筆後は、表現・語調・事実確認を中心に社内レビューを実施。SEO要素は構成時点で満たされているため、チェックを簡略化できます。 - 公開後の分析は外部に相談する
最初はSearch ConsoleやGA4の分析が難しい場合、公開後のデータ分析とリライト提案だけを外注するのも効果的です。
このように工程を分担すれば、外注コストを30〜50%ほど抑えながら、記事品質を維持できます。「社内にノウハウを残しつつ成果も出したい」企業にとって、ハイブリッド運用は最も現実的な方法と言えるでしょう。
発注を失敗させない要件定義と進行設計

SEO記事制作を外注する際に最も多い失敗は、「目的が曖昧なまま発注してしまうこと」です。
キーワードだけを渡して記事を書いてもらった結果、
「内容が浅い」「社内の意図とズレている」「思った成果につながらない」――そんな経験をした企業も少なくありません。SEOライティングの成果を安定させるには、発注前の要件定義と進行設計をどれだけ丁寧に行うかが鍵になります。ここを整えることで、ライターとの認識ギャップをなくし、スムーズに高品質な記事を量産できます。この章では、
- 発注前に準備しておくべき資料や情報
- 実際の制作フローとチェック体制
- 成果を正しく評価するための指標設定
など、実務担当者がすぐに使える要点を整理します。“ライター任せにならない発注”のための実践的なノウハウを解説していきましょう。
依頼前に準備すべき5つのドキュメント(検索意図・禁止表現・KPIなど)
SEOライターに記事を依頼する際、発注内容を明確に伝えることが成果の分かれ道になります。
そのためには、単なる「テーマ」や「キーワード」だけでなく、記事の目的や前提を共有できる資料を事前に整えておくことが大切です。ここでは、実際の制作支援でも重視している「5つの基本ドキュメント」を紹介します。
① 検索意図ブリーフ(検索目的の整理)
まず最も重要なのが、「なぜそのキーワードで記事を書くのか」を明文化すること。ユーザーの検索意図(調べたい・比較したい・購入したいなど)を整理し、この記事で何を解決するか」を1〜2行で書き出すだけでも、ライターの理解度が格段に上がります。
記載例:
- キーワード:「SEOライターとは」
- 検索意図:SEOライターとWebライターの違いを理解したい/発注判断をしたい
- 記事目的:SEOライターへの依頼検討を促す
② 禁止・注意表現リスト
記事品質を守るためには、使ってほしくない表現やトーンを明確にしておきましょう。企業によっては「他社比較を避ける」「専門用語を多用しない」「カジュアルな口調を控える」など、トーン&マナーに違いがあります。これを共有しておくと、初稿段階での修正工数を大幅に削減できます。ブランドガイドラインがある場合は、抜粋して添付するのも効果的です。
③ KPI設定シート
SEOライティングは“成果を測る記事制作”です。そのため、記事公開後にどの指標で成果を判断するか(KPI)をあらかじめ共有することが重要です。
KPI例:
- 公開30日後の検索順位(主要キーワード3位以内)
- CTR(クリック率)2.5%以上
- CVR(問い合わせ・資料DLなど)1%以上
このように、ライターがゴールを理解して執筆できる状態をつくることで、成果を狙いやすくなります。
④ 参考記事・競合情報
「どのようなトーン・深さ・構成で書いてほしいか」を共有するために、参考記事3〜5本と、その評価ポイントを示しておくとスムーズです。
例:
- A社記事:構成がわかりやすく、図解が参考になる
- B社記事:内容は網羅的だが、専門性が浅いので差別化できそう
こうした比較コメントを添えることで、ライターが「どこを伸ばし、どこを避けるべきか」を明確に理解できます。
記事制作のワークフロー ─ キーワード選定から公開・分析まで
SEO記事制作は、「書く」だけで完結する仕事ではありません。
キーワード選定から公開後の分析までを一連の流れとして管理することで、はじめて継続的に成果が出ます。ここでは、企業が外注・内製いずれの場合でも活用できる、基本のワークフローを紹介します。
① キーワード選定と検索意図分析
最初のステップは、「何のキーワードで」「どんな目的で」記事を書くかを明確にすることです。
キーワードは単に検索ボリュームの多い言葉ではなく、自社の顧客層が抱える疑問や課題と結びつくものを選びます。キーワードを選定したら、検索上位10記事を確認し、どんな課題を解決しているか
・どんな構成や表現が多いか
・自社が提供できる独自の価値は何かを分析します。この時点で「検索意図の深さ」を正確に把握しておくことで、後の構成づくりがブレません。
② 構成設計(見出し構成・情報設計)
次に、検索意図をもとに見出し構成(H2・H3)を設計します。ここで意識したいのは、「読者がどの順番で疑問を解消するか」というストーリーラインです。
・導入部で共感を生む
・問題提起 → 解決策 → 具体例 → まとめ
という流れを設計し、記事を最後まで読ませる構成を目指します。構成案には、想定読者の課題・含めたいキーワード・各見出しの狙い(検索意図)・を明記すると、ライター・編集者双方が同じ目的で制作を進められます。
③ 執筆・編集
構成が固まったら、本文執筆に進みます。執筆時は「検索エンジンの評価」と「読者の読みやすさ」のバランスが重要です。
- 見出しごとに“結論→根拠→具体例”の順で書く
- 小見出し(H3)で段階的に疑問を解消する
- 図表・リスト・引用を使って視覚的に整理する
執筆後は、第三者視点のレビューを必ず入れましょう。特に企業記事では表現・事実確認・ブランドトーンの統一が欠かせません。
④ 公開・計測
公開後は、記事を“出して終わり”にせず、数値で評価するステップへ移行します。代表的な指標は以下の通りです。
| 指標 | 内容 | 目安 |
| 掲載順位 | 検索順位の推移をモニタリング | 3か月以内に10位以内が理想 |
| CTR(クリック率) | 検索結果からのクリック率 | 2〜5%前後を目標 |
| CVR(成果率) | 記事内リンクからの行動率 | サービス紹介記事で1〜2%程度 |
これらの数値をSearch ConsoleやGA4で確認し、次のリライトや記事企画に活かします。
⑤ 改善・リライト
SEO記事は、公開してからが本当のスタートです。掲載順位やCTRが低い場合は、タイトル・見出し・構成を見直し、データに基づいたリライトを行いましょう。特に有効なのは、
- ユーザーが離脱している見出しを改善する
- 検索上位の新しい競合記事を分析する
- 内部リンクを整理し、回遊性を上げる
撮影ティブでは、公開30日後・60日後を目安に簡易分析を行い、改善提案を行うケースが多いです。
こうした定期的なレビューサイクルが、“継続的に伸びるメディア”を作る最大のポイントです。このように、SEO記事制作は「分析 → 構成 → 執筆 → 計測 → 改善」という5ステップの循環型プロセスで成り立っています。単発ではなく、この流れを仕組み化できるかどうかが、成果の出る企業とそうでない企業の分岐点です。
成果を正しく測る指標(Search Console/GA4)
SEO記事の価値は、「公開したかどうか」ではなく、「読まれ、行動につながったかどうか」で判断すべきです。しかし実際には、「何を見れば成果が出ているのか分からない」という声も少なくありません。
ここでは、Search ConsoleとGA4(Google アナリティクス4)を使った基本的な評価指標を整理します。
① 検索パフォーマンス(Search Console)
| 指標 | 内容 | 着目ポイント |
| 掲載順位 | 検索結果での平均順位 | 10位以内を目安。3か月以内に上昇傾向があるかを確認。 |
| クリック率(CTR) | 表示されたうちクリックされた割合 | タイトル・メタディスクリプションの改善指標。1〜3%未満なら要見直し。 |
| 表示回数(IMP) | 検索結果での露出回数 | トピックの需要と露出状況を把握。改善の“伸びしろ”を測る。 |
たとえば、順位は上がっているのにCTRが低い場合、タイトルの訴求力や検索意図とのズレを疑う必要があります。このように、Search Consoleのデータは「記事をどう改善すべきか」を見極める重要な材料になります。
② 行動データ(GA4)
GA4では、記事に訪れたユーザーがどのような行動を取ったかを確認します。SEOの目的が「流入の増加」だけでなく「問い合わせ・資料請求・商品購入」などである場合、GA4の指標がKPIになります。
| 指標 | 内容 | 活用例 |
| セッション数 | 記事を訪れた回数 | 流入トレンドを把握(週・月単位で推移確認) |
| 平均エンゲージメント時間 | 記事の滞在時間 | 内容の読み応え・興味度を確認(60秒以上が目安) |
| コンバージョン(CV) | 記事経由で発生した行動 | 資料DL・問い合わせ・EC購入などの成果指標 |
特に「平均エンゲージメント時間」は、記事の満足度を測るうえで重要です。滞在時間が短い場合は、導入文や見出しの順序、画像の使い方を見直すことで改善できます。
③ 期間と目標の設定
SEOの成果は即時には出ません。記事公開から約1か月で掲載順位が安定し始め、3か月で傾向が見えてくるのが一般的です。そのため、次のような“評価サイクル”を設定するのがおすすめです。
- 公開後14日:インデックス状況を確認
- 公開後30日:順位・CTRを初回チェック
- 公開後60日:改善点を洗い出し、タイトルや構成を微調整
- 公開後90日:KPI(流入・CV)で最終評価
このように「評価時期」をあらかじめ決めておくと、チーム内で成果を共有しやすくなります。
まとめ:データを“評価”で終わらせない
数値を見る目的は、“記事の良し悪しを判断する”ことではありません。むしろ、「次にどこを改善すべきか」を発見することこそが計測の意義です。Search Consoleで“読まれる力”を、GA4で“行動を生む力”を可視化する――
この2つの視点をセットで追うことで、SEO記事を単なるコンテンツから事業貢献する資産へと育てていくことができます。
契約・修正・著作権で気をつけるポイント
SEO記事制作を外注する際は、記事の品質だけでなく、契約面・修正対応・著作権の取り扱いにも注意が必要です。これらを曖昧にしたまま進めると、納品後のトラブルや再利用時の制約につながることがあります。ここでは、発注前に確認しておくべき3つのポイントを整理します。
① 契約範囲の明確化
まず重要なのは、「どこまでを依頼範囲に含むか」を契約書や発注書で明記することです。
記事制作では、執筆以外にも次のような工程が発生します。
- キーワード選定・構成作成
- 画像選定・入稿作業
- 修正対応・リライト提案
これらを「含む・含まない」が明確でないと、納品後に追加費用が発生する可能性があります。初回打ち合わせ時に「制作工程ごとの担当範囲」を確認し、認識をそろえるようにすることが重要です。
② 修正対応ルールの取り決め
SEO記事では、初稿から完全な形に仕上がることはほとんどありません。特に検索意図やトーン調整など、確認が必要な箇所は複数回発生します。そのため、*修正対応の回数・範囲・期限」を事前に決めておくと安心です。
③ 著作権・二次利用の取り扱い
SEO記事の著作権は、契約形態によって帰属が異なります。
一般的には、制作会社やライターが著作者となりますが、発注時に「著作権譲渡」や「利用許諾範囲」を明記することで、自社サイトや資料などへの再利用が可能になります。
また、以下の点にも注意が必要です。
- AI生成文や外部引用を使用する場合、出典・著作権表記を明確にする
- ライターが他クライアントへ同内容を再利用しない旨を契約書に盛り込む
- 自社がリライト・再編集する権利を確保しておく
記事は一度公開したら“資産”になります。後から自由に編集・再利用できるよう、法的な権利関係は発注時に整理しておくことが鉄則です。
まとめ:安心して任せるために「契約も設計の一部」と考える
SEO記事制作は、クリエイティブな工程でありながら、同時にビジネス契約でもあります。
「制作」「修正」「著作権」それぞれの条件を事前に明文化することは、ライター・企業の双方にとって信頼関係を築く第一歩です。契約時にこの3項目を丁寧にすり合わせることで、後工程でのトラブルを防ぎ、安心して制作に集中できる体制を整えておきましょう。
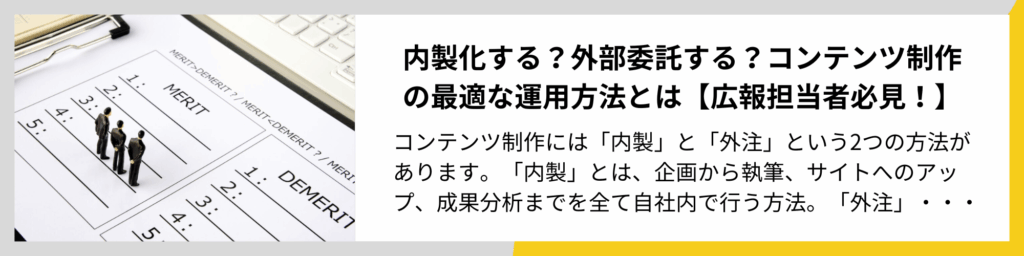
よくある質問(FAQ)
SEO記事制作やSEOライターへの依頼を検討する際、担当者からよく寄せられる質問をまとめました。初めてSEOライティングを外注する方、社内での体制づくりに悩む方は、ここで基本を押さえておくと安心です。
Q1. SEO戦略の立案と目標設定は誰が行うべきですか?
SEO戦略の立案は、企業のマーケティング担当者とライターが協働して行うのが理想です。記事単体で成果を追うのではなく、事業目標やフェーズに合わせて「何を狙う記事なのか」をすり合わせましょう。
キーワード分析と目的設計をセットで行い、企業の方向性に沿ったSEO計画を立てていきましょう。
記事1本あたりの料金相場は?
記事内容や依頼範囲によりますが、
- 執筆のみ:1〜3万円前後
- 構成+執筆:3〜6万円前後
- 分析・改善提案込み:6〜10万円以上
が一般的な目安です。単価だけで比較せず、「構成を誰が作るのか」「改善提案まで含まれているか」を確認しましょう。
納期の目安はどれくらい?
1記事あたりの制作期間は、構成+執筆で2〜3週間前後が一般的です。社内確認や修正回数によって変動するため、余裕を持ったスケジュール設計が大切です。複数記事をまとめて発注する場合は、週単位でリリーススケジュールを組むと安定した運用が可能です。
未経験でもSEOライターに依頼できますか?
もちろん可能です。
発注側がSEOに詳しくなくても、目的と成果指標を共有できれば十分対応可能です。撮影ティブでは、キーワード設計・構成案の段階から伴走し、初めての担当者でもスムーズに進められる体制を整えています。
画像や図版の準備は誰が担当するのですか?
基本的には、文章制作と画像制作は分業です。ただし、記事内容に合わせて図解や構成案にビジュアル要素を提案するSEOライターもいます。自社で画像制作が難しい場合は、制作会社に構成+デザイン込みで依頼するのがおすすめです。
引用や著作権の注意点はありますか?
SEO記事で他サイトや統計データを引用する場合は、出典の明記が必須です。
引用の範囲を超えて転載すると著作権侵害になる可能性があるため、
- 出典元の名称・URLを明記
- 引用部分を明確に区切る(“ ”やblockquoteを使用)
ことを徹底しましょう。
また、画像素材は必ず商用利用可のものを使用し、ライター任せにしないのが安全です。
まとめ:SEO記事制作支援
SEO記事制作は、検索順位を上げることがゴールではありません。本来の目的は、企業の想いやサービスを、必要としている人に正しく届けることです。撮影ティブでは、SEOの技術だけにとどまらず、
「伝えたいこと」と「検索で求められていること」をつなぐ編集支援を行っています。単なる外注先ではなく、広報・マーケティング担当者の伴走パートナーとして、記事構成・執筆までを一貫してサポートします。たとえば
- 自社のトーンを活かした記事構成が作れない
- SEOの方向性が定まらず、発信の軸がブレている
- 外注しても“成果”に結びつかない
そんな課題を感じている企業に、撮影ティブの伴走型支援は最適です。“成果が出る仕組み”を一緒に育てていくことを大切にしています。
「どんな記事を出せば成果につながるのか」「SEOライターに何を任せるべきか」――
そんな疑問が浮かんだときは、まず一度ご相談ください。
丁寧なヒアリングを通して、自社に合った最適な記事制作の形をご提案します。