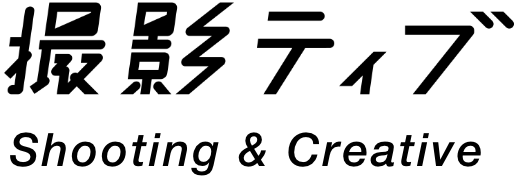広報とマーケティングはどう連携する?効果を高めるコツと成功の秘訣

しかし現場では「広報とマーケティングの違いがよくわからない」「部署ごとに動いていて一体感がない」といった課題も少なくありません。本記事では、広報とマーケティングの基本的な定義や役割の違いを整理しつつ、連携によって得られるメリットや、効果を高めるための実践的なコツを解説します。
ブランド価値を高めたい方や、売上拡大を目指す広報・マーケティング担当者にとって、明日からの取り組みに役立つヒントをまとめました。
目次
広報とマーケティングの定義と違い

広報は、企業の信頼性やブランドイメージを社会やステークホルダーに伝える役割を担い、直接的な売上よりも「企業の価値や存在意義」を長期的に育てる活動です。一方でマーケティングは、顧客ニーズの把握から商品・サービスの提供までを設計し、売上や成長といった短中期的な成果に直結する活動といえます。
ここからは、広報とマーケティングの定義を改めて整理し、それぞれがどのような目的を持ち、どのように進化してきたのかを見ていきましょう。
広報とは?企業コミュニケーションの基本
広報とは、企業が社会や顧客、取引先、メディアなどのステークホルダーに対して情報を発信し、信頼関係を築く活動を指します。単に「会社の情報を伝える」だけでなく、企業の存在意義やブランド価値を長期的に育てるための重要な役割を担っています。
広報活動の具体例には、プレスリリースの配信、メディア対応、イベントの企画、CSR活動の発信などがあります。これらは直接的に売上を生むものではありませんが、企業の信頼性を高め、社会的評価を向上させる効果があります。
また広報は、一方的な発信だけでなく「社会の声を受け取る」役割も果たします。社会の期待や課題を企業活動に反映させることで、より持続可能で共感を得られるブランドづくりにつながります。
つまり広報は、「企業と社会をつなぐ架け橋」 として、企業が長期的に成長するための土台を築く存在なのです。
マーケティングとは?商品・サービスを売る仕組み
マーケティングとは、顧客のニーズを理解し、それに応える商品やサービスを設計・提供することで、売上や企業成長につなげる仕組みづくりを指します。単なる広告や販売促進活動のことではなく、「市場調査から商品企画、プロモーション、販売、顧客との関係構築」までを含む包括的な活動 です。
具体的には、ターゲットとなる顧客層を分析し、そのニーズに合わせた商品・サービスを開発。さらに効果的なプロモーションやチャネルを選定し、購買へとつなげます。購買後の顧客体験やアフターフォローもマーケティングの重要な一部であり、継続的な顧客関係を築くことで、リピート購入やブランドロイヤリティの向上を図ります。
つまりマーケティングは、「商品やサービスを通じて顧客との関係を生み出し、維持し、発展させる活動」 です。短期的な売上だけでなく、企業の長期的な成長を支える基盤ともいえます。
広報とマーケティングの目的の違いを整理
広報とマーケティングの目的は似ているようでいて、アプローチや成果の指標は大きく異なります。以下の表に整理すると、その違いがよりわかりやすくなります。
【広報とマーケティングの目的の違い】
| 項目 | 広報 | マーケティング |
| 主な目的 | 企業の信頼性やブランドイメージを高める | 売上や利益の拡大を実現する |
| ゴール | 社会的評価・長期的なブランド価値の向上 | 顧客獲得・購買促進・市場シェア拡大 |
| アプローチ | 情報発信・メディア対応・社会との関係構築 | 顧客ニーズ調査・商品開発・販促活動 |
| 成果の指標 | メディア露出、好意度、企業の認知度 | 売上、利益、ROI、顧客満足度 |
| 時間軸 | 中長期的 | 短中期的 |
このように、広報は「信頼やブランド価値を育てる長期的な活動」マーケティングは「顧客ニーズに応え、売上をつくる短期〜中期的な活動」と位置づけられます。
歴史的背景と進化から見る両者の関係
広報とマーケティングは、時代の変化とともに進化してきました。もともとは独立した活動として存在していた両者ですが、デジタル化の進展や顧客接点の多様化によって、その境界線は次第に曖昧になりつつあります。
かつての広報は主にメディア対応や社外への情報発信が中心でした。一方マーケティングは、広告や販売促進を通じて顧客を獲得することが主眼でした。しかし、インターネットやSNSの普及により、顧客は企業情報を自ら検索し、社会的な評価を参考に購買行動を取るようになりました。
この変化によって、広報が担う「信頼やブランド価値の発信」と、マーケティングが担う「顧客獲得や売上拡大」の活動は切り離せない関係となり、両者が連携して戦略を立てることが企業の成長に不可欠 になっています。
広報とマーケティングの役割の違いと具体例

広報とマーケティングは目的が異なるだけでなく、日々の業務やアウトプットにも明確な違いがあります。広報は「企業やブランドの信頼を育てるための活動」が中心であり、メディアとの関係構築や社会的責任の発信など、直接的な売上には結びつかないけれど、企業の存在価値を支える役割 を担います。
一方、マーケティングは「顧客に商品やサービスを届け、売上をつくるための活動」が主軸です。市場調査やプロモーション企画など、顧客の購買行動を促進し、成果を数値で測定できる業務 が多く含まれます。
ここからは、具体的に広報とマーケティングが果たす役割をいくつかの視点で比較し、実務にどう違いが表れるのかを見ていきましょう。
企業イメージやブランド価値を高める広報
広報の大きな役割のひとつが、企業イメージを形成し、ブランド価値を高めることです。商品やサービスそのものだけでなく、「企業そのものがどのように社会から見られているか」 は、顧客の購買行動や信頼獲得に大きく影響します。
たとえば、プレスリリースやメディア露出を通じて企業の取り組みを正しく伝えることで、社会からの認知度や好感度を高めることができます。また、CSR活動やサステナビリティに関する発信は、単なるイメージアップにとどまらず、「信頼される企業」という評価 を育てる要素となります。
さらにSNS時代においては、顧客が企業の情報を検索・共有する機会が増えているため、広報による一貫した情報発信はブランド価値の維持・強化に直結します。短期的な売上だけでなく、長期的に選ばれる企業となるために、広報は欠かせない役割を担っているのです。
売上につなげるマーケティングのプロモーション
マーケティングの役割の中心にあるのは、商品やサービスを顧客に届け、実際の購買につなげることです。そのために欠かせないのが、プロモーション活動です。プロモーションとは、広告やキャンペーン、イベント、SNS活用などを通じて、顧客に購買を促すための一連の施策を指します。
たとえば新商品を発売する際、マーケティングはターゲット顧客を明確にし、その層に効果的に届くプロモーションを企画・実行します。テレビCMやWeb広告、SNSでのキャンペーン、インフルエンサーとのタイアップなど、多様なチャネルを組み合わせることで、認知拡大から購買行動までを設計します。
広報が「企業全体の信頼やブランドイメージ」を育てるのに対し、マーケティングは「顧客の購買行動を促進し、売上をつくる」ことを直接的なゴールとしています。その成果は売上高やROI(投資対効果)といった数値で測定できる点も特徴です。
利害関係者と顧客へのコミュニケーションの違い
広報とマーケティングのもう一つの大きな違いは、コミュニケーションの対象です。広報が向き合うのは、顧客だけではありません。株主、投資家、行政、地域社会、メディアなど、企業を取り巻く幅広い利害関係者(ステークホルダー)が対象となります。広報活動を通じて「社会から信頼される企業」であることを示すことで、企業の持続的な成長を支える基盤を築きます。
一方、マーケティングが主に向き合うのは「商品やサービスを購入する顧客」です。市場調査やターゲット分析を行い、消費者心理を理解したうえで最適なメッセージを届け、購買につなげます。顧客のニーズに直接応えることがマーケティングの中心であり、その成果は売上や顧客数として表れます。
つまり、広報は企業全体のステークホルダーとの信頼構築、マーケティングは顧客との関係構築 を目的とした活動であり、この対象の違いが役割の違いを明確にしているのです。
広報とマーケティングのメッセージ設計の違い
広報とマーケティングは、同じ「情報発信」を行う立場でありながら、そのメッセージ設計には明確な違いがあります。
広報のメッセージは、企業のビジョンや理念、社会的責任といった「企業全体の姿勢」を伝えることが中心です。伝える対象は幅広く、メディアや地域社会、投資家、従業員なども含まれるため、信頼感と一貫性 を持った発信が求められます。広報のメッセージは「長期的な企業イメージの形成」に寄与するのが特徴です。
一方、マーケティングのメッセージは、特定の商品やサービスを購入してもらうことを目的としています。顧客の関心や課題に直結する情報を届け、購買意欲を刺激するように設計されます。プロモーションや広告においては、短期的な成果につながる具体性と訴求力 が重視されるのです。
つまり、広報は「企業全体をどう見せるか」、マーケティングは「商品やサービスをどう売るか」という観点でメッセージを設計しており、この違いを理解することが両者の効果的な連携には欠かせません。
企業広報の役割と重要性

とくに近年は、SNSやオンラインメディアの普及により、企業の発信内容は瞬時に社会へ拡散し、企業イメージや評判に直結するようになりました。そのため広報の影響力はこれまで以上に大きく、戦略的な視点での取り組みが不可欠となっています。
広報が果たす役割は多岐にわたります。信頼性を高める情報発信や、万が一のトラブル時の危機管理、メディアとの関係構築、そしてCSR活動の発信など、いずれも企業の持続的な成長を支える柱となるものです。
ここからは、具体的に広報が担う4つの主要な役割と、その重要性について詳しく見ていきましょう。
信頼性を高める情報発信のポイント
企業が社会や顧客から信頼を得るためには、広報による情報発信の質が非常に重要です。どれほど優れた商品やサービスを持っていても、発信内容に一貫性や透明性がなければ、信頼は築けません。
信頼性を高めるための広報発信には、以下のようなポイントがあります。
・一貫性のあるメッセージ
企業の理念やビジョンに基づいた発信を続けることで、受け手に「ぶれない姿勢」を印象づけられます。
・透明性の担保
自社にとって不利な情報や課題も隠さず発信する姿勢は、長期的に見て企業への信頼を高めます。
・社会との対話
単なる一方通行の広報ではなく、SNSやイベントなどを通じて社会の声を受け取り、それを企業活動に反映させることも信頼性の強化につながります。
信頼性のある広報発信は、企業イメージを高めるだけでなく、将来的な危機対応の基盤にもなります。つまり広報は「良いときだけではなく、困難なときにも頼られる存在」であることが大切なのです。
危機管理・リスク対応での広報の役割
企業活動においては、製品トラブルや不祥事、自然災害など、予期せぬリスクや危機に直面することがあります。こうした非常時に重要となるのが、広報による迅速かつ適切な情報発信です。
危機管理における広報の役割は、大きく以下の3つに整理できます。
・迅速な情報開示
事実を隠すのではなく、正確でわかりやすい情報を速やかに発信することが、社会からの信頼を守る第一歩です。
・誠実な姿勢の表明
被害を受けた顧客や関係者に対して謝罪や対応策を明確に伝えることで、企業の姿勢を示し、信頼回復につなげます。
・一貫したメッセージ発信
社内外で情報が食い違うと混乱を招きます。広報が窓口となり、統一されたメッセージを出すことが重要です。
危機対応における広報は、単なる「情報の出し手」ではなく、企業の信頼を守り、回復させる最後の砦 です。平時からリスクを想定した広報体制を整えておくことで、有事の際に迅速で効果的な対応が可能になります。
メディアリレーション構築の重要性
広報活動において、メディアとの良好な関係構築(メディアリレーション)は欠かせない要素です。テレビ・新聞・雑誌・Webメディアなどは、依然として社会に大きな影響力を持っており、信頼性のある第三者視点からの報道は、企業の認知度やイメージを大きく左右します。良好なメディアリレーションを築くことで得られるメリットは以下の通りです。
・情報発信力の拡大
自社発信だけでは届かない層へも、メディアを通じて広く情報を届けられる。
・第三者による信頼性の付与
記事や番組で取り上げられることで、広告よりも高い信頼性が得られる。
・有事の対応力向上
トラブルや危機発生時に、信頼関係のあるメディアが正しい情報を拡散してくれる可能性が高まる。
そのため広報担当者は、プレスリリース配信や取材対応を単発の業務としてこなすのではなく、日常的に記者や編集者と信頼関係を築くことが重要です。メディアとのパートナーシップは、企業のブランド価値を支える長期的な資産 といえるでしょう。
CSR・社会的責任を広報で伝える意味
企業が持続的に成長するためには、利益の追求だけでなく、社会や環境に対する責任を果たす姿勢が求められます。CSR(企業の社会的責任)やサステナビリティへの取り組みは、顧客や投資家をはじめとしたステークホルダーにとって、企業選びの重要な基準となっています。
ここで広報が担うのは、単にCSR活動を「報告」することではなく、企業の姿勢や価値観をわかりやすく社会に伝えること です。例えば環境保護への取り組みや地域社会への貢献を発信することで、消費者は「この企業を応援したい」と感じやすくなり、長期的なブランドロイヤリティの向上につながります。
さらに、CSR広報は社内への浸透にも効果的です。従業員が自社の取り組みに誇りを持てるようになり、エンゲージメントの向上や人材採用にもプラスに働きます。
つまりCSRの広報は、外部への信頼獲得だけでなく、社内外に企業の価値を共有し、持続可能な成長を後押しする戦略的な役割 を果たしているのです。
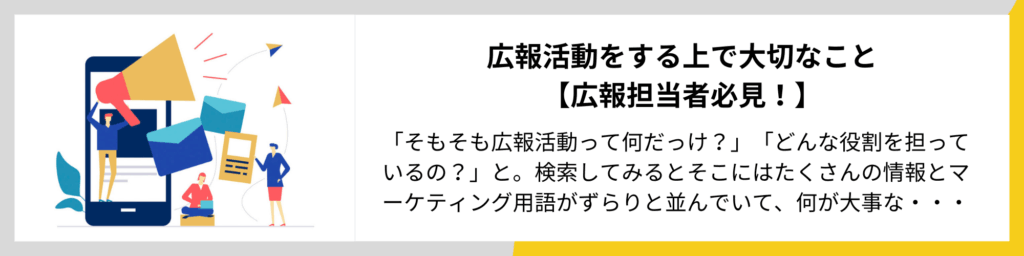
マーケティングの機能と効果

マーケティングは、企業が商品やサービスを市場に届け、顧客との関係を築きながら売上や成長につなげるための中心的な活動です。単なる広告や販売促進にとどまらず、市場調査から商品企画、プロモーション、販売後のフォローまでを包括的に設計するプロセス を含みます。
その機能は多岐にわたり、消費者ニーズを把握して戦略を立てることから、具体的な販促施策の実行、競合との差別化を図るポジショニング戦略、そして売上増加を実現するための成長戦略に至るまで幅広いものです。
ここからは、マーケティングが持つ代表的な機能と、それぞれが企業にどのような効果をもたらすのかを具体的に見ていきましょう。
消費者ニーズの調査・分析で戦略を作る
効果的なマーケティングの第一歩は、顧客が何を求めているのかを正確に把握することです。消費者ニーズを理解せずに商品やサービスを提供しても、市場とのミスマッチが生じ、売上にはつながりません。
そのために欠かせないのが市場調査とデータ分析です。アンケートやインタビュー、購買データの解析、SNS上の口コミ分析などを通じて、顧客の行動や価値観を把握します。こうした調査結果は、商品企画やプロモーション戦略に直結する重要な材料となります。
さらに最近では、AIやビッグデータを活用した高度な分析が進み、消費者の潜在的なニーズを予測することも可能になっています。これにより、単なる「現状把握」ではなく、未来を見据えた戦略立案が実現できます。
つまり、消費者ニーズを調査・分析し、戦略に落とし込むことがマーケティングの出発点 であり、成功する企業ほどこのプロセスに力を入れているのです。
効果的な販促活動の計画と実行
消費者ニーズを把握したら、それを具体的な行動につなげるのが販促活動です。販促(プロモーション)は、商品の魅力を伝え、顧客の購買意欲を喚起するための重要な施策であり、マーケティングの中心的な機能のひとつです。効果的な販促活動を行うためには、以下のようなステップが必要です。
ステップ① 目的とターゲットの明確化
認知拡大なのか購買促進なのかを整理し、どの顧客層に届けたいのかを定めます。
ステップ② チャネルと手法の選定
Web広告、SNSキャンペーン、イベント、店舗でのプロモーションなど、顧客に届きやすい手段を選びます。
ステップ③ 成果指標の設定と検証
コンバージョン率や売上増加など、成果を測定する指標をあらかじめ設定し、実施後に効果を検証します。
計画的に設計し、実行後のデータをもとに改善を繰り返すことで、販促活動はより効果を発揮します。単発のキャンペーンで終わらせるのではなく、中長期的な顧客育成を見据えたプロモーション戦略 が、売上拡大とブランド強化の両立につながるのです。
市場ポジショニング戦略で競合と差別化
競争が激しい市場の中で、自社の商品やサービスを際立たせるために重要なのが 市場ポジショニング戦略 です。ポジショニングとは、顧客の頭の中に「自社はどんな価値を提供する企業なのか」という明確な位置づけを築くことを指します。
具体的には、品質・価格・デザイン・利便性などの要素をもとに、自社が「どの立ち位置で競合と差別化するのか」を定めます。たとえば、低価格を強みにするのか、高品質・高付加価値を前面に出すのかによって、打ち出すメッセージもプロモーション戦略も大きく変わります。
さらに、近年は機能的な差別化だけでなく、ブランドストーリーや社会的価値といった「情緒的価値」もポジショニングの鍵となっています。消費者は単にモノを買うのではなく、「そのブランドを選ぶ理由」を求めているからです。
効果的なポジショニング戦略を築くことで、企業は顧客にとって唯一無二の存在となり、価格競争に巻き込まれない強いブランドを育てることができます。
売上拡大と企業成長につなげるマーケティング
マーケティングの最終的な目的は、商品やサービスを通じて売上を拡大し、企業の持続的な成長を実現することです。市場調査やプロモーション、ポジショニング戦略といった各プロセスは、そのための手段にほかなりません。
売上拡大を実現するためには、短期的なキャンペーンの成功だけでなく、顧客との長期的な関係構築 が欠かせません。リピート購入やサブスクリプションの導入、顧客満足度向上のためのカスタマーサポート強化など、継続的に顧客に価値を提供する仕組みが求められます。
さらに、データ分析を活用して購買行動を可視化し、効果的な改善を繰り返すことで、マーケティング施策の精度は高まります。これにより、限られた予算でも高いROI(投資対効果)を実現することが可能になります。
つまりマーケティングは、単なる「売るための活動」ではなく、企業を次の成長ステージへ導く戦略的な活動 なのです。
広報とマーケティングを連携させるメリットと成功のコツ

たとえば広報が築いた「企業への信頼」は、マーケティング活動における購買促進の後押しとなります。逆に、マーケティングで得られた顧客データや市場の声は、広報活動に活かすことでより社会と共感を生む発信が可能になります。
つまり、広報とマーケティングをうまく連携させることは、単なる業務の効率化ではなく、ブランド価値の向上と売上拡大を同時に実現するための鍵 なのです。
ここからは、両者を連携させることで得られる具体的なメリットと、その実践に役立つ成功のコツを紹介していきます。
一貫性のあるメッセージ発信で信頼を築く
広報とマーケティングが連携するうえで最も重要なのは、発信するメッセージの一貫性です。どれほど優れた商品やサービスであっても、広報とマーケティングが異なるメッセージを出してしまえば、受け手に混乱を与え、信頼を損ねる可能性があります。
一貫性のあるメッセージを発信するためには、以下の視点が欠かせません。
・企業理念に基づく情報発信
広報は社会やステークホルダーに、マーケティングは顧客にアプローチしますが、根底にある理念やブランドの方向性を共有することが大切です。
・ターゲットごとに適切に翻訳する
伝える対象によって言葉やチャネルを変えつつも、核となる価値観やビジョンは統一させます。
・長期的なブランドイメージを重視
広報が積み上げた信頼を、マーケティングが活かして購買促進につなげるという流れを意識すると、企業全体で一貫性を維持できます。
メッセージの一貫性は、短期的な売上だけでなく、長期的に選ばれるブランドを築く基盤 となります。広報とマーケティングが連携して同じ方向を向くことこそ、信頼を強化する第一歩です。
相乗効果でブランド力と集客力を高める
広報とマーケティングが連携することで得られる最大のメリットのひとつが、相乗効果によるブランド力と集客力の向上です。
広報は、社会に向けて企業の信頼性やブランド価値を築き上げる役割を担っています。一方でマーケティングは、商品やサービスの魅力を伝え、実際の購買行動へと導く活動を展開します。これらが連動すると、「信頼される企業だから商品を選ぶ」 という顧客心理が生まれ、単なる購買促進以上の効果を発揮します。
具体的には、広報が獲得したメディア露出やSNSでの評判を、マーケティング施策に活用することで認知拡大が加速し、集客力が大きく高まります。逆にマーケティング活動から得られた顧客の声を広報にフィードバックすれば、より共感を得られるストーリーテリングが可能になります。
このように広報とマーケティングは、それぞれの強みを掛け合わせることで 「ブランドの信頼」と「顧客の行動」を同時に強化する相乗効果 を実現できるのです。
データ共有で実現する戦略的な意思決定
広報とマーケティングの連携を強化するうえで欠かせないのが、データの共有です。両者が持つ情報を組み合わせることで、より精度の高い戦略的意思決定が可能になります。
マーケティングは、顧客属性や購買行動、広告効果といった数値データを豊富に持っています。一方、広報は、メディア露出や社会的評価、SNSでの反響など、企業イメージや信頼に関する定性的なデータを蓄積しています。
これらを共有・統合することで、以下のような効果が期待できます。
・顧客理解の深化
数字だけでは見えない顧客の心理や社会的評価を踏まえた戦略が立てられる。
・施策の最適化
広報の活動がブランド好感度を高めているか、マーケティング施策が売上にどの程度貢献しているかを総合的に評価できる。
・迅速な意思決定
データに基づいた判断が可能となり、経営層に対しても説得力のある報告ができる。
広報とマーケティングがデータを共有することで、感覚や経験に頼らない、科学的で戦略的な意思決定 が実現するのです。
成功事例から学ぶ広報とマーケティング連携のポイント
広報とマーケティングの連携を強化するには、実際の成功事例から学ぶことが近道です。うまく連動している企業は、単に部署間で情報をやり取りしているだけではなく、共通の目標と戦略を持ち、一体感を持った発信 を行っています。
たとえばある企業では、広報が獲得したメディア露出をマーケティングの広告素材として活用し、信頼性を高めながら認知拡大を実現しました。また別の企業では、マーケティングが集めた顧客データを広報が分析に取り入れ、社会から共感を得やすいストーリーを発信することでブランド価値を高めています。
こうした事例に共通しているポイントは以下の通りです。
・目標を共有する
「売上拡大」や「ブランドイメージ強化」など、両者が同じゴールを見据えて活動する。
・情報を双方向に活用する
広報のメディア露出をマーケティングに活かし、マーケティングの顧客データを広報に還元する。
・定期的な連携体制を整える
部署間ミーティングや共同プロジェクトを通じて、連携を日常業務に組み込む。
これらを実践することで、広報とマーケティングは単なる「別部署の活動」ではなく、企業成長を加速させる一体的な戦略 へと進化します。
まとめ 広報とマーケティング連携で成果を高めるために
広報とマーケティングは、それぞれ異なる目的と役割を持ちながらも、連携することで大きな成果を生み出せる活動です。広報が築いた「信頼」と「ブランド価値」は、マーケティングのプロモーション活動を後押しし、売上や集客につながります。一方で、マーケティングが収集した顧客データや市場の声は、広報の発信内容をより社会に響くものへと高めてくれます。
本記事では、広報とマーケティングの違いを整理したうえで、両者が協働することで得られるメリットや実践のコツを紹介しました。自社においても、まずは部門間で情報や目標を共有することから始めてみると、成果が変わり始めるはずです。
もし「自社に合った広報とマーケティングの連携方法がわからない」「戦略設計から伴走してほしい」と感じている方は、ぜひ専門家のサポートを検討してください。撮影ティブでは、外部広報として企業に伴走し、戦略立案からコンテンツ制作・SNS運用までトータルで支援いたします。